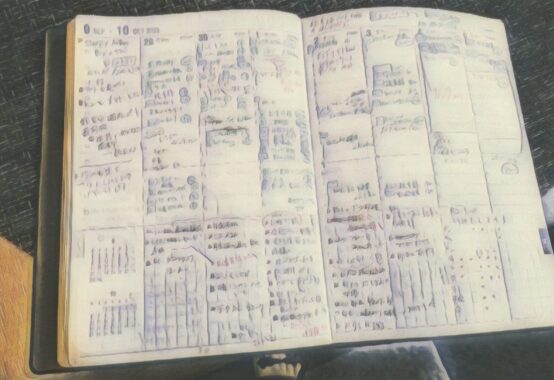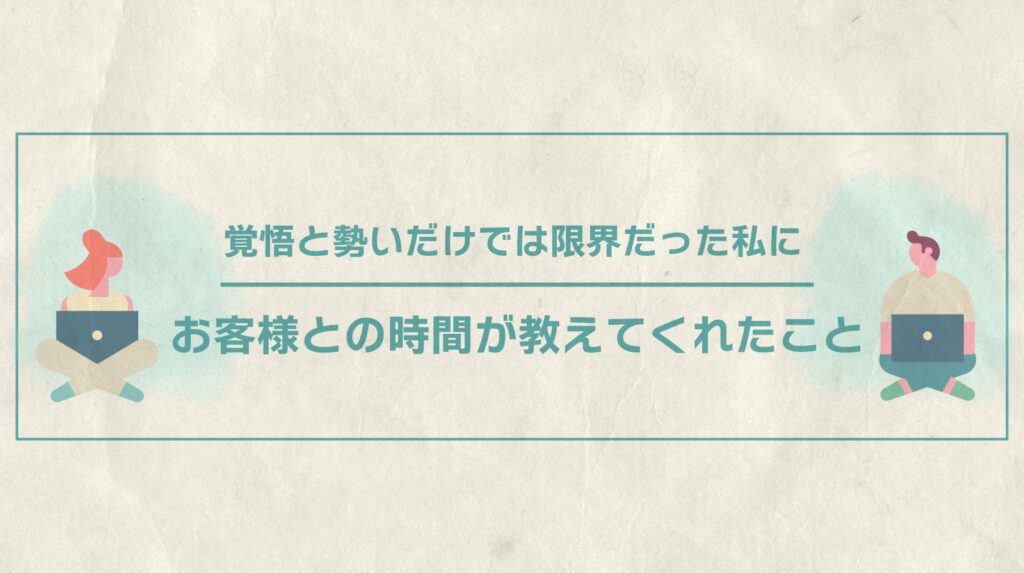
前回の記事「発信を止めていた私が得たもの」では、
私は「発信を止めていた期間も、ナーチャリングや既存顧客との関係づくりに力を注いでいた」と書きました。
実はその裏側で、同時に取り組んでいたことがあります。
それは、それは、「また動けるようになるための“支え”を整えること」でした。
後にそれが“仕組み”という形になっていきましたが、はじめから仕組みを作ろうとしたわけではありません。でした。
なぜ、仕組みづくりにこだわる必要があったのか。
そこには、私自身がかつて 「PMF(プロダクトマーケットフィット)後」
つまり、自分の事業が社会に受け入れられ始めた転換点で、大きくつまずいた経験 があります。
PMF前とPMF後:成長のフェーズ
スタートアップの世界では、「PMF(Product Market Fit)」という言葉がよく使われます。
ここでいうPMFとは、「自分の提供する価値が、一定の顧客層に支持され始める状態」を指します。
難しく聞こえますが、要は「事業が軌道に乗り始めるかどうか」を示す概念です。
PMF前(0→1):自分のサービスや商品が、本当に誰に選ばれるかを必死に模索する時期。
PMF後(1→10・拡張):ある程度の顧客に支持され、そこから事業を広げていく時期。
根性論では乗り切れなかった「拡張フェーズ」
私の起業初期は、まさにPMF前でした。
会社員を辞め、どこで自分は必要とされて、
いくらなら契約いただけるか分からなかった私は、
少しでも仕事をいただける可能性があるなら手弁当で動き回り、
ゼロからひとつずつ実績を積み上げていきました。
楽しさよりも、子どもたちを食べさせていけなくなる恐怖の方が勝っていて、
寝る間も惜しんで無我夢中で取り組んでいました。
そして、ある程度のお客様に選ばれるようになったとき、
私は次のフェーズ、PMF後=拡張フェーズへと足を踏み入れました。
ここからが、勢いでは乗り切れない、本当の意味で自分の力が試される段階だったのです。
PMF後でのつまずき ― 「仕組み」不足の代償
「仕組み」不足がチャンスを遠ざけた理由
私が大きく失敗したのは、お客様が増え始めた PMF後=拡張フェーズでした。
忙しさを言い訳に営業フローを見直さず、マニュアルや資料も整備しないまま、
「柔軟な対応」と言い訳しながら、実際は場当たり的な個別対応に頼りきっていたのです。
アルバイトや業務委託の方にお願いしても、
私の場当たり的なやり方では上手くいきませんでした。
そのツケはすぐにまわってきました。
お客様対応は後手後手になり、
新しい案件や商品開発に割ける時間はどんどん減っていったのです。
せっかく広がりかけていたチャンスが、
目の前からすり抜けていくのを眺めるしかありませんでした。
改善の目的が見えず、システム導入に走った過ち
同じことを繰り返さないために「この壁を乗り越えなければ」と思いながらも、
当時の私は 何のために改善するのかが見えていませんでした。
改善して時間ができたとしても、その時間をどう使うのか。
―当時の私は、「何をやめて」「何に時間をさくのか」という視点が欠けていました。
効率化やIT導入は目的ではなく、
あくまで「本当にやりたいことに集中するための手段」であることに、
当時はまだ気づけていなかったのです。
さらにコロナ禍もあり、世の中全体がデジタル化を急ぐ中で、
私も例外ではなく、自分の業務に合う仕組みを作るよりも、
とにかく便利そうなシステムを次々と導入してしまいました。
結果として、システムだけが増え、
現場の業務改善にはつながらない失敗を繰り返しました。
本当に必要だったのは、便利なツールを増やすことではなく、
「お客様の声を出発点に、時間の使い方そのものを見直すこと」でした。
その結果として「仕組み」という形に落とし込まれることもありますが、
仕組みはあくまで「考え方を形にする道具」にすぎません。
「宿題をしないお客様」からの学び
「宿題をしないお客様」から学んだ真実
もうひとつの大きな学びは、お客様との関係の中で気づいたことです。
月1回の打ち合わせだけでは進まない課題を、
「次の打ち合わせまでに3件アポをとりましょう」
「ヒアリングシートに記入してください」
など、宿題としてお願いしても、進捗が止まってしまうことがありました。
毎週確認しても進まないだけでなく、答えが返ってこなくなり、
次の打ち合わせでまた、同じことを言う。
気まずい空気になることもありました。
もちろん、お客様にはやらない、やれない理由があります。
上手くいっているときに何かをやってもらうことは簡単ですが、
上手くいかないときに何かやってもらうことは難しい。
毎週追い立てるだけでは効果はないと気づいたのです。
今のやり方で望む反応を得られないならば、自分の行動を変えるしかありません。
追い立てるのをやめて、「時間」を確保した理由
私は考えました。
事前に資料を読み込んできてもらうのではなく、
月1回の打ち合わせの際に共有する。
そして、打ち合わせ日とは別に「月1回の一緒に作業時間」を確保する方が、
たとえ月2~3時間だけだとしても前に進めるのではないか?
確信はなかったけども、そこに割く「時間」が欲しくなったのです。
仕組みが時間を生み、時間が目的を見つける
仕組みの本当の価値は、「止まっていた行動を動かすきっかけになること」です。
お客様と月に数時間一緒に作業する時間を確保できるようになると、
「お客様の行動が止まっている原因」が少しずつ見えてきました。
そして、お客様が本当にやりたいことが見えてきたのです。
ただ、ここまで書いておきながら、私もまだ道半ばです。
このやり方ではわかりにくかったのかもしれない、
あの説明が足りなかったのかもしれない。
日々、反省することも多々あります。
根性論の限界と、仕組みがもたらす本質的な価値
退路を断っただけでは勝てない
世の中には、
「覚悟を決めたら道がひらけた」
「退路を断ったから成功した」
といった言葉があふれています。
けれど実際の起業は、そんな夢物語のようにはいきません。
大切なのはスタートを切ったあと「その後をどう積み上げるか」です。
地道な努力を続け、成果が出ない日々にも耐え、
選んだ道のなかで選び直しを繰り返す。
退路を断っただけで勝てるなら、誰も苦労はしないのです。
いま振り返れば、あの時期に必要だったのは根性や気合いではありませんでした。
必要だったのは、私を支えてくれる仕組みでした。
そして、その仕組みが生み出す時間こそが、次なる目的を見つける鍵となったのです。
この結論に至ってからも、私自身、試行錯誤の途中であり、反省も尽きません。
しかし、仕組みづくりがもたらす時間の余裕こそが、
新しい挑戦や、本当にやりたいことを見つける土台となることを確信しています。
まとめ
起業は「退路を断つ」だけで勝てるものではありません。
大事なのは、PMFを超えたその先です。
仕組みがあるかどうかよりも、
その仕組みが「何のためにあるのか」が明確でなければ、成長はすぐに頭打ちになります。
そして、改善の先に「時間の使い道」が見えるからこそ、仕組みづくりには意味があります。
私自身、まだ試行錯誤の途中であり、反省も尽きません。
けれどその過程こそが、次の一歩を支える原点になっているのです。
【参考文献】
Peter Thiel, Zero to One (2014)
― 「0→1」と「1→n(拡張)」という対比を提示した著作。PMF前後の理解にも通じる視点を与えてくれる。
あとがき
「根性論」を捨て、自分を助けてくれる仕組みを持つこと。
それが、拡張フェーズでチャンスを掴む唯一の方法でした。
仕組みづくりで時間が生まれると、
「その時間を何に使いたいか」という次なる目的が必ず見えてきます。
そのために、まずは「場当たり的な対応をやめるためのルール」を
決めることから始めてみませんか。
運用の叩き台づくりから、一緒に前に進める仕組みの設計までご一緒します。
お気軽にご相談ください。
販促プランナー/マーケター
小売業やメーカーでの経験を活かし、販促企画・広報・デザインの支援を行っています。
2010年に個人事業として独立し、2018年に法人化。外国人販売員研修や販売促進支援を展開してきました。
現在は「ツヅケルマーケティング®」を軸に、
中小企業が“売れ続け・選ばれ続ける”仕組みづくりを伴走型でサポートしています。
「動けない」を「やってみよう」に変えるヒントを、このブログで発信しています。