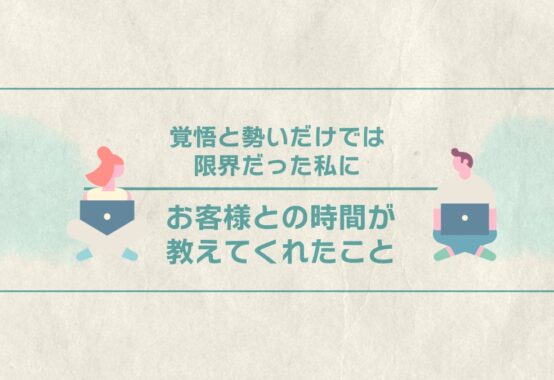こんにちは。合同会社ここからの野見山です。
日々の仕事の中で、
私は「ブランドをどう育てるか」という話を日々お客様と交わしています。
しかし、「どう守るか」について話し合う機会は、意外と少ないように感じます。
2025年、私は自社の活動を通じて大切にしてきた
「ツヅケルマーケティング®」を商標登録しました。
この経験を通じて実感したのは、商標は「特別な企業のための制度」ではなく、
中小企業こそ早く取り組むべき経営の基盤だということです。
SNS時代の商標トラブルは、誰にでも起こり得る
SNSやYouTubeをはじめ、個人でも発信力を持てる時代になりました。
広告費をかけずとも、1つの投稿が一気に拡散されることも珍しくありません。
その一方で、サービス名やブランド名が他社の商標と似ている場合、
突然「商標権侵害ではないか」と指摘を受けるケースも増えています。
実際の裁判事例:「#シャルマントサック事件」
たとえば、2021年に大阪地裁で判決が下された「シャルマントサック事件」では、
フリマアプリで出品者が正規品ではないバッグに「#シャルマントサック」と
ハッシュタグを付けた行為が、商標権侵害と認定されました。
つまり「検索用にハッシュタグを付けただけ」でも、
ブランドの信用を利用した行為と見なされる可能性があるということです。
SNSで商品やサービスを紹介する行為そのものが、
いまや「広告」と同じ法的影響を持ち始めています。
これは大企業だけでなく、すべての発信者が直面する新しい現実です。
出願の前にできる、商標リスクのセルフチェック
商標登録は「専門家にしかできない難しい手続き」と思われがちですが、
今ではオンラインで基本的なチェックを自分でも行うことができます。
以下の項目を確認するだけでも、リスクを大きく減らすことができます。
コピペで使える「商標リスクセルフチェックリスト」
| チェック項目 | 確認内容 | 対応状況(○/△/×) | 備考・次のアクション |
|---|---|---|---|
| ① 類似商標の有無 | J-PlatPatで同一または類似の商標が出願・登録されていないか確認したか? | ||
| ② 区分の選定 | 現在と将来の事業範囲を考慮して、適切な区分を選定しているか? | ||
| ③ ロゴ・表記統一 | サービス名・ロゴ・SNSアカウント名などの表記が統一されているか? | ||
| ④ 登録後の更新管理 | 商標権の登録日・更新期限・区分を一覧管理しているか? | ||
| ⑤ SNS・Web表記の統一 | 公式サイト、LP、SNSなどでブランド名の表記揺れがないか? | ||
| ⑥ 模倣・無断使用の検知 | Google画像検索やChatGPTなどで模倣・無断使用を定期的に確認しているか? |
✅ コピーしてメモやスプレッドシートに貼り付け、各項目を「○/△/×」で評価しながら記入すれば、あなたのブランドの法務リスクがひと目でわかります。
Toreruが中小企業に広げた「法務の現実解」
私が今回利用したのは、オンライン商標出願サービスのToreru(トレル)です。

弁理士にすべて依頼するほどの予算はないけれど、
完全な自己流では不安という中小企業にとって、まさに現実的な選択肢でした。
Toreruを使えば、Web上で手続きの流れが可視化され、
必要な書類や区分の選び方も、専門家のサポートを受けながら進められます。
【Toreruが向くケース】
目的:コストを抑えて最低限の権利を確保
商標の特徴:類似が少なく、名称がシンプル
規模:国内中心の小規模事業
【弁理士への依頼が向くケース】
目的:複数区分を戦略的に押さえたい
商標の特徴:競合が多く、侵害判断が難しい
規模:海外展開・ライセンス契約を視野に入れる
Toreruと弁理士は対立するものではなく、
状況に応じて併用できるパートナーです。
登録して終わりにしない「ブランド防衛の3ステップ」
商標登録はスタートラインです。
登録後も、ブランドを守るために定期的な確認が欠かせません。
商標権の更新管理表を作る
Googleスプレッドシートで「登録日・区分・更新期限」を一覧化しておくと安心です。
SNS・Webサイトのブランド統一チェック
LPやプロフィール欄の表記揺れを定期的に確認しましょう。
模倣・無断使用の検知
Google画像検索やChatGPTの類似検出機能を活用することで、早期発見が可能です。
こうした地道な運用が、商標の「登録」から「ブランド資産化」への橋渡しになります。
まとめ:「育てる」と「守る」は、ひとつの経営活動です
マーケティングの世界では「ブランドを育てる」ことが重視されますが、
育てるには“守る仕組み”が欠かせません。
SNS時代では、ブランドは発信と同時に広がり、同時にリスクにもさらされます。
Toreruのようなツールが登場したことで、
法務の知識がなくても、自社の名前を守る選択肢が現実的になりました。
「ブランドを続ける力を支えるのは、法の仕組みでもある」
私はそう実感しています。
参考情報
判例・一次情報
- 大阪地裁 令和3年9月27日判決(いわゆる「#シャルマントサック事件」)の評釈PDF・判決データ(事実関係・判断枠組みの確認に使用)。
出典:Lex Law Library
公的データベース
- 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(商標の類否検索の解説や公式概要の参照に使用)。
公式サービス情報(Toreru)
- Toreru公式サイト(サービス概要/出願の流れ・サポート体制等の確認)。
- PR TIMES(ToreruのAI調査など、機能リリース関連情報の補助確認)。
有識者・法律事務所による解説(二次情報)
- 日本弁理士会系誌「パテント」論文「ハッシュタグと商標」(関連裁判例の俯瞰と位置づけ確認)。
- モノリス法律事務所(事件解説・実務的示唆の参照)。
販促プランナー/マーケター
小売業やメーカーでの経験を活かし、販促企画・広報・デザインの支援を行っています。
2010年に個人事業として独立し、2018年に法人化。外国人販売員研修や販売促進支援を展開してきました。
現在は「ツヅケルマーケティング®」を軸に、
中小企業が“売れ続け・選ばれ続ける”仕組みづくりを伴走型でサポートしています。
「動けない」を「やってみよう」に変えるヒントを、このブログで発信しています。